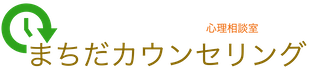見出し一覧
はじめに
自傷行為と聞くとどのような行動を想像しますか?リストカットや薬品の過剰服薬であるオーバードーズ(OD)などがこの行動に当てはまります。端から見ると「なぜそのような苦しい選択を自ら行うのか」という疑問が当然湧いてくることでしょうし、近しい人物の行動に怒りの気持ちを持つ方もいらっしゃるかもしれません。
本コラムでは自傷行為の背景にある気持ちについて考え、カウンセリングではどのように扱っていくのかを考察していきたいと思います。

自傷行為の現状
1割近い方が生涯に一度は自傷行為を経験しているという報告があります。その後の人生でずっと続くことは稀で、一過性のもので終わる方がほとんどだとは思いますが、決して無視のできない数字ではないでしょうか。特に思春期は対人関係で大きく揺れ動く時期であるため、この年代で自傷行為の頻度が高いことは当然のことなのかもしれません。現に先ほどご紹介した生涯の自傷経験率と女子高生の自傷経験率はそこまで大きな数値上の差はないようです。
自傷行為の種類
さて、自傷行為と言うと、最初にご紹介したリストカットが最も知られたものでしょう。続けて市販薬過剰服薬は近年広まっている方法です。肉体に傷を付ける方法は人それぞれですが、あまり詳細に描写したくないので、このコラムでは主にリストカットとオーバードーズについて述べようと思っています。
また、身体を傷つけること以外でも広い意味での自傷行為と言える行動があります。例えばギャンブルや過度な飲酒によって、自分の生活が成り立たない中で過ごしているのであれば、この行為も自傷行為と同じ意味があるのではないでしょうか。(参考:依存に関する悩みについて)
ここに挙げたどの行動も自分に益するものはありません。しかし、ご本人にとっては無くてはならない行動でもあるのです。他人からは理解し難くとも、何かしらの必要性があると考える方がよいでしょう。
背景にある2つの気持ち
自傷行為を行うときは、もうどうでもいいという諦めに似た気持ちと、この苦しい状況から誰かに救い出してもらいたいという気持ちがあるようです。行動だけ見ると自己破壊的で投げやりになっているように見えますが、心の底には状況が変わって欲しいという声があることを知っておくことが大切です。多くの場合、2つの気持ちの間で板挟みとなって激しい葛藤が生じているはずです。自傷行為の苦しみとはこの板挟みの状態が続くことかもしれません。
自傷行為に含まれる意味の移り変わり
自傷行為は何度も繰り返されることによって、その意味が変わってくるように感じることがあります。初期と常態化したときの気持ちを比較してみます。
最初は生きるための行動
自傷行為を初めて行うときは痛みや虚無感を伴います。リストカットであれば実際に切る痛み、そして、自分は何をしているのかという虚しさです。ですが、この時に生じる生々しい感情は自分が今ここに存在しているという証拠であると感じられ、自身を現実に留めるためのピンのような役割を果たすことになります。リストカットを行う方の中には「切っている時だけ生きている気がする」と仰る方がいます。この安心感や高揚感が繰り返しへと繋がるきっかけとなるのでしょう。
慣れが生じて常態化へ
自傷行為が繰り返されることによって徐々に慣れが生じてきます。当初の安心感や高揚感を実感しにくくなるのです。すると、より危険で激しい行為へと進むことで気持ちの高まりを得るようになっていきます。
さて、この段階では自傷行為の背景にあった2つの気持ちを達成する事は目的ではなくなり、行為そのものが目的となっているように感じます。自傷行為は気持ちを行動で表現したものではなく、依存性のある嗜癖という段階へと進んでいることになります。
自傷行為の依存性
自傷行為が常態化していくに従って、行動の意味が変わっていくことは伝わったでしょうか。最初は他者を求める気持ちが叶わずに、虚になっている心をなんとか留め置こうとする意味がありました。しかし、徐々に行為そのものが目的となっていきます。他者へのメッセージ性が失われていき、自身の中で情緒を賦活させるための行動として自傷行為が行われるようになります。
自傷行為を行う理由
さて、初期の自傷行為には自らが生きるためにピンを打つ意味があると述べました。裏を返せばピンを打たないと自身の存在に実感が持ちにくいということでもあるのでしょう。このような実存的な欲求が満たされない状況とは、どんなことが影響しているのでしょうか。少し考えてみたいと思います。
人間関係が途絶えたと感じている
学生時代に友達と不仲になり、このことが自傷行為へと繋がる方がいらっしゃいます。思春期では集団の中で同調していることが非常に大事です。仲違いは大人が想像する以上に孤立感を高めます。人とのつながりが途切れたことによって自分を繋ぎ止めるものが何もなくなったと体験されるのかもしれません。もちろん、そこには苦しさを周囲に分かってほしいというメッセージもあるのでしょう。
人間関係の変化から生じる自傷行為は、集団に属する年齢であれば周囲が気付くことも少なくありません。どなたかが支えとなることで常態化することを予防できるため、早期の発見とケアが大切となります。
他者に支えられている確信がない
一昔前は自傷行為が保護者の養育の問題とされていた時期もあるようです。しかし、決してそのようなことはなく、本人の受け止め方や性格の影響があることは疑いがないでしょう。しかし、何らかのやむを得ない事情によって養育者と十分な関われなかった子供時代を過ごされた方がいることは事実です。
一般的に幼い時期には養育者が子どもの気持ちを察して、それに合わせた適切な対応をしてくれます。このやりとりを通して、子どもは自分が一人ではないことや世界と安全に繋がっていることを感じますし、思い通りにならない体験は自分と他者が別物であることを知るきっかけとなります。しかし、十分な体験が積み重なっていないと、子どもは自分が一人であり世界は恐れに満ちていると感じるようになります。助けて欲しい気持ちはあっても期待は叶わないことが当然という世界の中で過ごすことになるのです。
この気持ちをいつまでも自分の中に置いておくことはあまりにも苦しいため、外に追い出そうとします。このことが自分を傷つけることに繋がっていきます。それは、満たしてもらえない自分を合理化するための価値下げの意味があるのかもしれませんし、激しい情緒の嵐で不快な感情を上書きしようとしているのかもしれません。
現実への影響
自傷行為があまりに重篤なものであれば、対人面や職業上の不適応という形で問題が生じてくることが当然考えられます。激しい自傷を行えば家族や友人から心配をされますが、時間の経過と共に関心を払われないばかりか呆れられたり、怒りをぶつけられるようになります。また、自身が受け止めてもらえないと感じた時の解消や、不快な気持ちを追い出すための手段として自傷行為が習慣となっていれば、徐々に激しくなる上に終わりの見えない状態が続くことが想像できます。
また、自傷行為がエスカレートすることで違法薬物など法に触れる行為に手を染める方も少なからずいます。このことが現実生活に与える影響についての説明は不要でしょう。
自傷行為の話題に触れることは大事
よくある誤解は、心身を危険にさらす行動が繰り返されるが既遂とならないことから「本当は死ぬ気などない」と当事者の苦しみを軽く考えてしまうことです。これは非常に危険な受け止め方です。当事者の葛藤する気持ちに目が向いていないと、注意を引く行動としての意味付けしか出来なくなってしまいます。しかし、助けてという声が十分に受け止めてもらえないと、もう一方の諦めの気持ちが強くなってしまうのです。
上述したように自傷行為は徐々にエスカレートしていきます。段々と過激になっていく行動に周囲は無力感を感じたり呆れて距離を取ることが多いですが、この変化もまたご本人の諦めの気持ちを強くさせてしまうでしょう。結果、周囲が自傷行為を気に留めないことは取り返しのつかない状況へと繋がる可能性を増加させてしまいます。
松本(2009)がリストカットをされている患者の10年後生存率などを調査しています。この結果を参照すると、自傷行為を行う患者の死のリスクは明らかに平均値を上回っています。自傷行為が決して関わりを持ってもらうための誇張された表現や、注意引きという認識だけでは済まないことがお分かり頂けるのではないでしょうか。(参考:話を聴く時のポイント)
カウンセリングでは
カウンセリングで自傷行為を話題にするのであれば、自傷行為に至ったきっかけや経緯を話題にすることから始まると思います。そして実際に行動に起こした場面の前後の気持ちを振り返ることが必要になるでしょう。おそらくある部分まで話が進むと上手く言葉にできないことに気が付くはずです。それは、あなたを守る心の働きから生じていることなので、急いで明確にする必要はありません。少し触れて、また戻るということを時間をかけて行なっていきます。
ここまでで自傷行為には孤独感や諦めなどの苦しい気持ちが伴うことを見てきました。当然、カウンセリングで話題にする負担も大きくなります。ときにカウンセリングをやめたくなることもあるでしょうが、来室の足を止めないことを頑張ってみてください。そして、カウンセラーにも負担が高いことを伝えてください。負担に押しつぶされない無理のないペースを探していくことが、とても大事なことなのです。
また、自傷行為のエピソードは人間関係や性格のことをお話ししている時に並行して話題に上がることが多いです。自己理解が進むことによって自傷行為の意味が自然と分かることもありますから、様々な場面に焦点を当ててお話をしてみても良いかもしれません。
参考
- 松本俊彦(2009), 自傷行為の理解と援助, 日本評論社.
- B.W.ウォルシュ(著), 松木邦裕(訳)(2007). 自傷行為治療ガイド, 金剛出版.