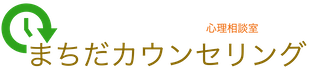見出し一覧
はじめに
2021年、厚生労働省と文部科学省がヤングケアラーの支援方法を模索していくという発表を行いました。ヤングケアラーとは状態像を指す言葉であり、特定の疾患や障害を表すものではありません。しかし、子どもや若者が背負う負担が大きくなることで、現在の生活の質のみならず、生涯に渡る多大な影響を及ぼす危険があることに留意をする必要があります。
本記事ではヤングケアラーがどのような方を指しているのか、そして当事者がどのようなことに直面しているのかをお伝えできればと考えています。

ケアラーの負担
家族に介護が必要な高齢者がいらっしゃったり、お世話が必要な幼児さんがいる場合、身の回りのお手伝いをする家族の存在がどうしても必要になります。このような支える役割を担っている人物はケアラーと呼ばれます。介護や育児の負担が大きくなることでケアラーの疲労感も増し、時に気持ちの落ち込みなどの心理的症状を伴うことも起こり得ます。家族を支えることは尊い行為ですが、そこにある当事者の悩みは外からは見えにくいものであり、当事者が一人で苦しんでいることがあるのです。
ヤングケアラーとは
多くの場合、介護や育児の担い手は家庭内の大人が引き受けることが多いですが、様々な事情から大人ではなく子どもがケアラーの役割を担うことがあります。
日本ケアラー連盟のホームページなどを参照すると「大人が担うようなケアの責任を引き受けている18歳未満の子ども」がヤングケアラーの定義となるようです。主に障害や病気のある親や祖父母の介護への従事が多いようですが、兄弟や親戚のお世話をしていることもあるそうです。以下にヤングケアラーの例をあげてみます。
- 障害や病気のある家族の代わりに家事全般を担当している。
- 幼い兄弟や障害のある兄弟の日常生活のお世話をしている。
- 精神疾患のある家族を支えている。
- 家計を支えるためにやむなく就労している。
何が課題なのか
家族を支えている彼らは何も間違ったことはしていません。しかし、留意すべきことは彼らが子どもであり就学年齢であることです。ケアを提供することの負担によって、友人を作る時間が持てなかったり、自分が成長する機会を失ってしまえば、自らの人生を生きることが難しくなります。
特に就学や就職に影響が出るのであれば、自己犠牲的な献身を行なっていると言わざるを得ないでしょう。当事者となっている子ども本人は既に当然の日常となっているのかもしれませんが、彼らが18歳未満であれば、本人が問題ないと言っているから大丈夫という自己決定の原則を当てはめるのはまだ時期尚早だと思われます。
ヤングケアラーの実態は見えにくい
家族間で生じている支援者と被支援者の関係は表に見えづらい傾向があります。ヤングケアラーの場合はこの傾向がより顕著になるようです。理由の一つに世間一般の思い込みが作用していることも挙げられそうです。「支援は大人が行うものであり子どもが従事することはない」というこれまでの常識的な価値観の存在です。このような意識が前提として頭にあると、目の前にいる子どもが、ケアラーとしての役割を担っていることにに気付かなかったり、その負担を過小評価しやすくなります。
さらに、ヤングケアラーであるお子さんは年齢以上にしっかりとしていることが多く、我慢強くもあります。この傾向によって大人は実際の負担よりも軽く見てしまうことが生じやすいようです。家庭以外で子どもが過ごす生活の場は学校ですが、学校の先生やスクールカウンセラーからも日々大きな問題もなく過ごしていると見なされてしまい、手助けが必要な状況であることに気付かれずに見過ごされてしまう子どもがいることに留意しておく必要があるでしょう。
きっかけは何か?
さて、子どもがヤングケアラーとなるきっかけはなんでしょうか。多くの場合は家庭や大人側の事情であることは間違いないでしょう。例えば、貧困などの影響から大人が仕事に出掛ける時間が増えたといった事情や、突然、介護や育児が必要になったなどの状況が考えられます。また、大人が家庭環境を維持することに無関心であれば、子どもが家族を繋ぎ止めようと尽力することも考えられます。前者は切実で現実的な事情がありますが、後者は大人側に意識の変化を求めざるをえません。
ですが、どちらの事情であっても、ヤングケアラーとしての役割が継続的なものになっていないかどうかがポイントのようにも思います。一時的に子どもにお願いすることは仕方ない場面もあるでしょう。しかし、子どもの役割の範囲が徐々に広がり、かつ長期間に渡るものとして固定化されていくようであれば、緊急事態のやむを得ない対応とは異なります。
子どもの負担があまりにも大きければ虐待と遜色ない環境に置かれていると判断されることもあるでしょう。この場合は、子どもへの心理的ケアも必要になるかもしれません。
参考:児童虐待を取り巻く状況
行政の施策
ヤングケアラーをめぐって、行政では家庭と子どもの支援を手厚くする方針を打ち出しています。子どもがアクセスできるようなオンライン相談体制の設置や、SNSを用いた会員交流の場を作るなどの動きがあります。また、相談機関の理解を促すために、福祉や教育などの分野の専門員への研修を企画していく方針が2021年にスタートしています。
上記はヤングケアラーを見える化する施策ということができるでしょう。しかし、根本的な解決はやはり家庭へ福祉的援助が届きやすくすることであり、経済支援や人手支援などを行っていく必要があるのではないかと思います。
気になる子どもがいた時にどうするか
大事なことは家族以外の人物がなるべく早くに状況を把握することです。学校での早期発見は勿論ですが、近隣家庭で子どもが家族をケアしている様子を頻繁に見かけるようであれば、是非、継続的に気にかけて頂き、可能であれば声をかけることが大きな一歩となります。
多くの場合、子どもたちは仕方なく当然のことをしていると思っています。確かに必要なことではあるのですが、子どもたちが行なっていることを良いことと太鼓判を押してしまうと、ヤングケアラーとしての役割を肯定することになってしまいます。また、保護者や近しい大人を責めることも違います。子どもたちにとっては大切な人なわけですから悪者にされてしまうと、余計に家族以外の人物に実情を話すことに抵抗を感じるようになってしまうはずです。状況を知り、子どもが気兼ねなく話せる人物が現れることが、時間は掛かりますが確実な一歩ではないでしょうか。
福祉窓口につながるために
長期的には行政の福祉窓口につながることは必要です。そのために子どもと同居している大人の理解を得ることが必要になりますが、家族以外の立場で促すことはなかなかに難しいことです。役所の子ども家庭支援センターなどに一報を入れることや、子どもの所属する学校に状況を伝えるだけでも改善の一歩となりますので、お電話の労をお引き受け頂くだけでも大きな支えになります。
まずは環境改善から
ヤングケアラーの当事者からカウンセリングの申し込みをすることは多くはないでしょう。学校や習い事などの生活の場で生じる会話の中でふと子どもが実情を吐露するということによって状況に気付くことが多いでしょうから、大人の観察力や推測する力が求められるはずです。
虐待に近いような状況でお子さんが過ごされているようであれば、心理支援を行うことも考えられますが、その場合も福祉的援助を整えた上で実施することになるはずです。つまり、優先事項は現実的な環境改善であると言って差し支えないかと思います。
カウンセリングの出番はいつか
心理カウンセリングの出番はヤングケアラーの方が成人になって、過去の自分を振り返る必要が生じた時かなと思われます。そこには、青春の時間を自由に過ごせなかった悲しみや憤りの感情が含まれているはずです。そして、その気持ちを向ける先がないことが大きな苦しみとなっていることが考えられるでしょう。漂うのは閉塞感であり、前に進めず、やり直すことも出来ないかつてのヤングケアラーの苦悩があるはずです。
どんな話をしていくことが良いのか
これからの人生の話も重要ですが、まずは子ども時代に得られなかったものが何かを十分に話題にして、どのようなものが欲しかったのかを自覚することが大切です。堂々と「大変だった。けど頑張った。」と言えるようになれることから始められると良いでしょう。置き去りにしてきた感情にしっかりと触れることは、ヤングケアラーの当事者が気持ちの落ち着く場所を探すためには欠かせない時間であるように思います。
おわりに
一昔前にアダルトチルドレンという言葉がありました。狭義にはアルコール依存症の両親を持ち親役割を担っていた子どもたちを指す言葉です。ヤングケアラーという言葉はこの言葉よりももっと幅が広いものですが、成人になってから抱える苦悩には似た部分があるように感じます。繰り返しになりますが、ヤングケアラーとしての役割そのものは褒められて然るべきです。しかし、そこに搾取の性格が含まれていないかを我々大人はしっかりと注意を払っておく必要があるようです。
参考
- 厚生労働省HP:(外部リンク)